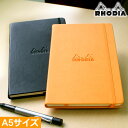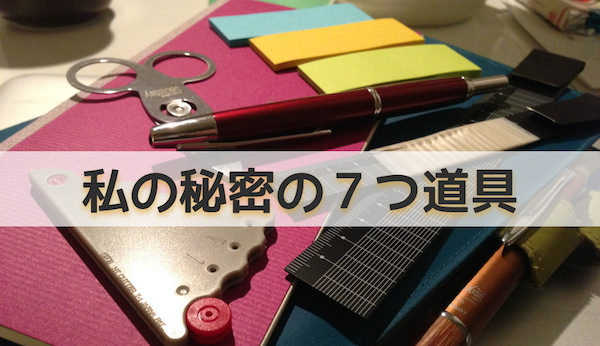万年筆を買うのであれば、ある程度の値段を出して、良い物を買うべきだ。そう思っていた。
しかし、このLAMY社のサファリを手にしてからは、そんな考えを止めなければいけないことを悟ったのだ。
もちろん、2万以上のお金を払って買う万年筆は最高だ。力を全く込めずとも、金のペン先からは潤沢なインクが流れ出てくる。あの滑らかな感触は何とも代え難いものだ。
ただ、それが全てではない。安いスチールのペン先であっても、これはこれで “使いがっての良い物” である。そのことを認めなくてはならない。
どちらもそれぞれに特徴があって、その特徴が人によってはピッタリとハマるだろう。特にLAMY社のサファリは、これから初めて万年筆を触る人と、私のように高い万年筆しか触ったことのなかった人に対してオススメしたい一品である。
※ラミー社の万年筆には、軸の素材が違う「サファリ」と「アルスター」という2つのタイプがある。厳密には違う商品だが、便宜を図るため、当記事では「アルスター」も含めて「サファリ」と記述している部分がある。ご了承頂きたい。

■価格がリーズナブル
真っ先に思い浮かぶ特徴は、なんと言っても価格だろう。
普通の万年筆が数万円の値札をぶら下げているのに対して、サファリは桁がひとつ違う。樋口一葉氏を握りしめてさえいれば買えてしまうのだ。
この値段であっても、メーカーは安心のLAMY社。ドイツの有名ブランドであるため、品質は折り紙つきだ。どこのものとも分からない中国品と一緒にしてはいけない。
高い万年筆は、それだけ手元が震える。「高価なものほど大切にしたい…」と考えてしまい、なかなかラフに使い込めないのが人の心だ(本来であれば、高いものほど使い込んでいきたいものだが…)。
そういう点でも、安いというのは嬉しい。恐れがないからラフに使っていける。いつでもどこでも使うには、これぐらいの値段の物のほうが気持ち穏やかに使っていける。
▼ここでは¥2,580で販売している。
■カラーバリエーション
サファリのラインナップは豊富だ。いろんなカラーがある。
サファリと同じデザイン・作りで、軸の素材が違う「アルスター」というタイプもあり、これを含めればその種類は10種類を超えてくる。(※「アルスター」と「サファリ」の違いは後述しています)
原色に近い鮮やかな色ばかりなので、日本人好みかとは言えないかもしれない。しかし、その色の豊富さは、選ぶ楽しさを与えてくれる。
特に「スケルトン」や「ホワイト」、そして「限定カラー」は非常に魅力的だ。
私が購入したシャンパンゴールド(アルスター)も、この2013年の限定カラーだ。…限定。この言葉だけでニヤニヤが止まらない。
■鉛筆のような書き味
これが褒め言葉かどうかは別にして、サファリの書き味は硬い。スチール製のペン先が故に、そのペン先は固めであり、印象としては「鉛筆で書いた時のようなカリカリ感」がある。
万年筆の最大の魅力である「ぬるぬるとした書き味」「力を入れなくても引ける線」とは違い、手には紙にひっつくような感覚が残る。
ただ、私はこれが逆に楽しい。多少筆圧が強くても、ペン先が曲がることがないので安心して書ける。ボールペンなどと同じような感覚で使えることから、「万年筆とボールペンの間の子」と言えるかもしれない。
初めて万年筆を触る人にオススメ。そう言っているのは、これが理由だ。
■重心
サファリでは2つの重心を楽しめる。自分の使いやすい方を選ぶといい。
ひとつは、キャップをペンの後ろに指すことで、重心を中心から後ろにかけることができる。万年筆を使う場合には、非常にオーソドックスな形だ。これにより、ペン先を寝かせることができ、力を入れずにスッと書いていける。
もうひとつは、キャップと付けない書き方だ。こうすると、重心が前(ペン先)にかかり、ペンを立てて使うことができる。
万年筆は通常、あまりペンを立てては使わない。寝かせて使うからこそ、あの滑らかな書き味を達成できるのだ。しかしサファリのペン先が硬いので、ペン先を立てて使っていても問題を感じることはない。
ボールペンの延長のように、今までと同じ感覚で使えるので、初めて万年筆を使う人にもきっと使いやすいだろう。
■選ぶ時の注意点
LAMYのサファリには、厳密に言うと2つのレパートリーがある。通常「サファリ」と呼んでいるタイプのものと、「アルスター」と呼ばれるタイプだ。
この2つの違いは、ペン軸の素材にある。通常のサファリが樹脂(プラスチック)で出来ているのに対して、アルスターはアルミで出来ている。そして、アルスターの方がペン軸が太く作られているのだ。
また、値段も少し違うので、気になる人は以下の2つのリンクを見比べてから、自分の好みのタイプを選んでもらいたい。
▼こちらが「サファリ」の一覧
▼こちらが「アルスター」の一覧
■あとがき:万年筆が私は好きだ
やはり私は万年筆の書き味が好きだ。インクの色が好きだ。万年筆で書き記したノートには、ボールペンでは成し得ない深みと味を感じる。
万年筆に敷居の高さを感じている人は、ぜひラフな気持ちで触ってみて欲しい。安物の万年筆を嫌悪している人にも、ぜひ触ってみて欲しい。
LAMYのサファリは、老若男女、誰に対してもオススメできる一品であると改めて感じた。
それでは、今日はこのあたりで。
from your @bamka_t